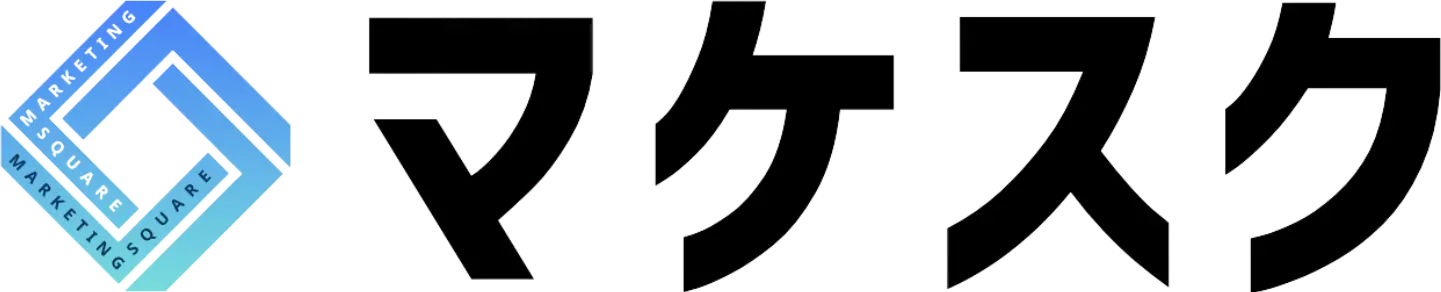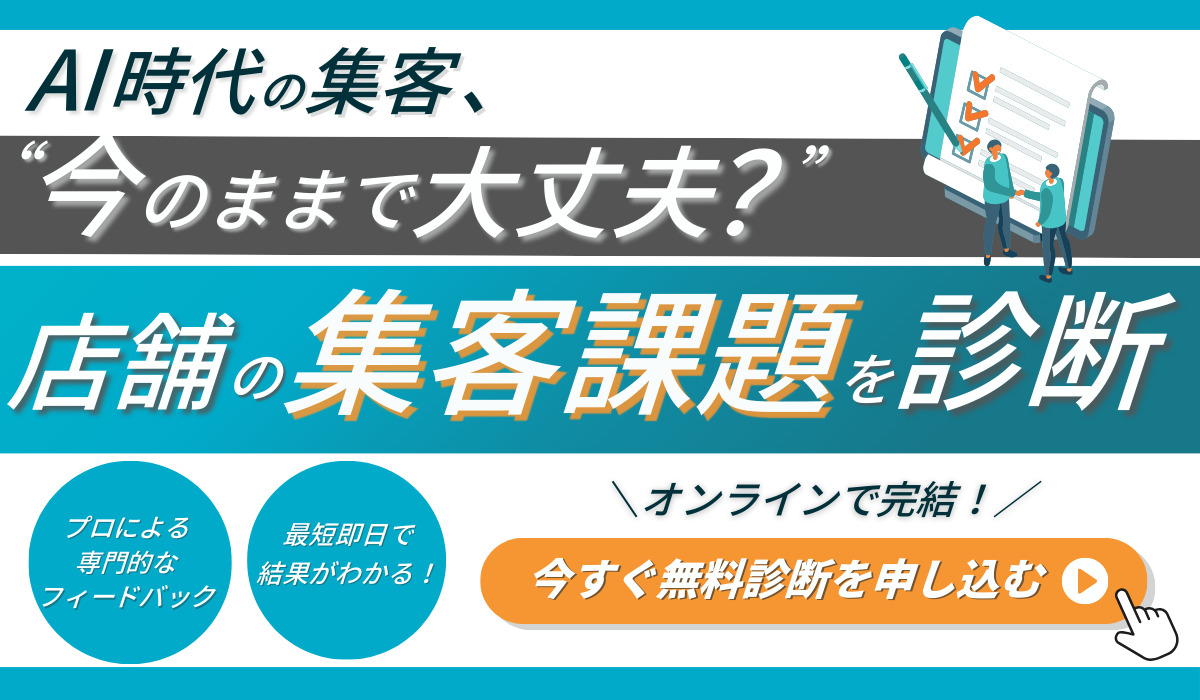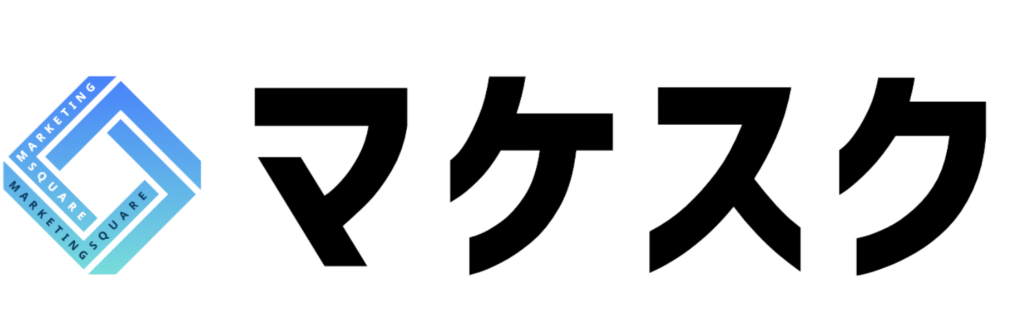居酒屋・バーのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法

訪日外国人観光客に選ばれる居酒屋・バーになるには、どのような対策が必要なのでしょうか?
インバウンド需要が回復する今、競合に差をつけるためには、戦略的な集客対策が欠かせません。
本記事では、多言語対応やSNS活用など、インバウンド集客の工夫が求められる今、選ばれる店舗になるための具体的な対策と実践方法をご紹介します。
なぜ今、居酒屋・バーにインバウンド対策が必要なのか?
訪日外国人観光客の増加により、居酒屋やバーがインバウンド需要を取り込むチャンスが広がっています。
この流れに対応するためには、今のうちから具体的な対策に取り組むことが重要です。
訪日外国人市場の回復と今後の成長予測
居酒屋・バーがインバウンド対策を進めるべき最大の理由は、訪日外国人市場の急速な回復と今後の成長が見込まれているからです。
観光庁の統計によると、2024年には新型コロナウイルスによる渡航制限が緩和され、多くの外国人観光客が日本を訪れるようになりました。
特にアジア圏や欧米豪からの観光客の回復が顕著であり、コロナ前の水準に戻りつつあるだけでなく、今後のさらなる増加が期待されています。
さらに、日本政府が掲げる「観光立国」の政策も追い風となり、宿泊・交通・飲食業界には安定的なインバウンド需要が見込まれています。
こうした背景から、居酒屋やバーが今のうちに対応を進めておくことが、今後の安定経営につながるのです。
訪日観光客の飲食支出と居酒屋・バーの需要
訪日観光客の多くが、滞在中の楽しみとして日本の「食文化」に強い関心を持っています。
観光庁の調査によれば、外国人旅行者の支出のうち、飲食費は常に上位を占めており、宿泊費に次いで高い割合を示しています。
特に居酒屋やバーは、日本らしい体験を提供できる場所として評価され、現地の雰囲気や日本酒、焼酎などへの興味から来店が促進されています。
また、団体客だけでなく個人旅行者やリピーターにとっても、ローカルな居酒屋は魅力的な観光コンテンツの1つです。
こうした傾向は今後も継続すると考えられ、飲食業界にとってはインバウンド対応を強化することが売上拡大の大きな機会です。
インバウンド対応を怠ると生じる機会損失
訪日外国人の来店ニーズに応えられない場合、他店に顧客を奪われるおそれがあります。
具体的には、多言語対応がないことや、キャッシュレス決済に非対応なことが来店の障壁となるでしょう。
また、Googleマップでの検索やSNSでの情報収集が主流となっている現在、オンライン上での情報不足が集客に直結してしまいます。
競合店舗が積極的にインバウンド対策を講じている中、何も対応していない店舗は「選ばれない店」になりかねません。
売上の一部が競合に流出するだけでなく、ブランド価値の低下にもつながるため、経営上のリスクを回避するためには、今のうちからインバウンド対策を備えておくことが重要です。
訪日外国人はどのようにして居酒屋・バーを探すのか?
訪日外国人が日本で飲食店を探す方法は、日本人とは異なる傾向があります。
検索経路を理解することで、効果的な集客施策を展開することが可能です。
Googleマップ・クチコミサイトでの探し方
訪日外国人の多くは、目的地周辺で飲食店を探す際にGoogleマップを利用します。
日本語が読めなくても、翻訳機能や画像で雰囲気を確認できるため、非常に利便性が高いと評価されています。
また、TripadvisorやYelpなどの海外向けクチコミサイトも多くの旅行者に活用されています。これらのプラットフォームでは、位置情報・評価・料理ジャンル・営業時間などを簡単に比較できるため、飲食店選びにおいて重要な判断材料です。
Googleビジネスプロフィールの最適化を行うことで、検索結果に表示されやすくなり、来店の可能性が高まります。
SNS(Instagram・小紅書)での探し方
訪日外国人観光客は、視覚的な情報に基づいて店を選ぶ傾向が強いため、SNSの活用が非常に重要です。
Instagramでは「#tokyofood」「#japaneseizakaya」などのハッシュタグ検索により、料理の写真や店内の雰囲気を確認し、来店の参考にしています。
特に若年層や女性旅行者には、見た目の印象が大きく影響するため、写真の質や投稿内容が集客に直結します。
また、中国圏では小紅書(RED)の利用が主流であり、旅行記や体験談形式の投稿が信頼されやすく、大きな影響力を持っています。
公式アカウントやインフルエンサーとの連携を図ることで、情報拡散力を高め、訪日外国人からの注目度を向上させることが可能です。
OTA・旅行サイトからの探し方
旅行の計画段階から飲食店を事前に調べる訪日客も増えています。
そうした旅行者は、ExpediaやBooking.comなどのOTA(オンライン旅行代理店)や、るるぶ・一休.comなどの旅行サイトを通じて飲食情報にアクセスしています。
旅行予約のついでにレストランのレビューや特集記事を確認し、滞在中に訪れる飲食店を選ぶ流れが一般的になりつつあります。
また、旅行パッケージにグルメプランが組み込まれていることもあり、掲載店舗は事前予約というかたちで安定した集客を見込めます。
自店の魅力が分かりやすく伝わる情報を整備して、こうした予約経路に対応することで、集客の幅を広げられます。
クチコミ・レビューの影響力
訪日観光客にとって、他者の評価や体験談は非常に大きな判断材料です。
星の数だけでなく、コメント内容や写真、外国語でのレビューが安心感を与え、来店動機につながります。
特に「英語でレビューされている」「中国語のコメントがある」といった点は、同じ言語圏の旅行者にとって大きな信頼要素です。
実際に、日本語の情報が一切ない店舗よりも、少しでも多言語レビューが掲載されている店舗のほうが高い集客効果を示しています。
継続的にポジティブなレビューを獲得できるように、接客品質を保ちつつ、自然なかたちでレビューを促す仕組みを取り入れましょう。
居酒屋・バーが実践すべき具体的なインバウンド対策
訪日外国人の来店を増やすためには、戦略的かつ実践的な施策の導入が欠かせないポイントです。
店舗の魅力を最大限に伝え、安心して利用してもらえるような準備を行うことが重要です。
MEO(Googleビジネスプロフィール)の最適化
店舗情報を正確に管理し、検索結果に上位表示させるためには、Googleビジネスプロフィールの最適化が欠かせません。
訪日観光客の多くがGoogleマップを使って飲食店を検索するため、オンライン上での情報整備が来店の可否を左右します。
営業時間や住所、メニュー写真、多言語対応の紹介文、支払方法などを充実させておくことで、訪日外国人観光客に安心感を与えられます。
また、クチコミへの返信や最新情報の更新を継続的に行うことで、店舗の信頼性と検索順位の向上が期待できます。
定期的な見直しと運用体制の整備を行い、Googleマップ上で選ばれる店舗づくりを進めていきましょう。
SNS運用とインフルエンサー活用
視覚的な魅力を重視する訪日外国人観光客には、SNSによる情報発信が効果的です。
特にInstagramやFacebookでは、料理写真や内装、スタッフの笑顔などが来店動機につながる要素です。日々の営業風景やおすすめメニューを発信することで、旅行前に情報収集をしている層への訴求が可能です。
さらに、信頼性のあるインフルエンサーと連携することで、店舗の魅力を第三者の目線で紹介してもらえます。
SNS投稿は単なる宣伝ではなく「日本の文化体験」として共感を得る内容が支持されやすいため、工夫を凝らした運用が求められます。
多言語対応メニューと店内案内
言語の壁を取り除くために、多言語対応の整備は非常に重要です。
訪日外国人客が安心して注文できるよう、英語・中国語・韓国語などに翻訳されたメニューを用意することが基本です。
しかし、ただ単に料理名を翻訳するだけでなく、写真や食材の説明を加えることで、料理内容への理解を深められます。
また、トイレや喫煙所、会計場所といった案内表示も多言語で掲示することで、店内での混乱を防ぐことが可能です。
さらに、スタッフが言葉に不安を感じる場合でも、適切な表示やツールを活用することで、訪日外国人観光客への対応品質を維持できます。
キャッシュレス決済導入(Alipay・WeChat Pay)
訪日外国人観光客の利便性を高めるためには、キャッシュレス決済の導入が求められます。
中国からの旅行者にとってはAlipayやWeChat Payが広く浸透しており、現金を持ち歩かないケースも珍しくありません。
対応していないことで、来店を見送られる場合もあるため、支払い手段を多様化することは集客にとって非常に重要です。
導入コストや手数料を不安に感じる店舗もありますが、実際には導入のハードルが年々下がってきており、手軽に対応できるようになっています。
キャッシュレス対応は単なるサービスの拡充にとどまらず、選ばれる店舗としての条件の1つになりつつあります。
訪日外国人客向けの人気メニュー・体験型サービスの設計
居酒屋・バーで提供される体験は、日本文化に触れる貴重な機会として訪日外国人客に人気です。
たとえば、地酒の飲み比べセットや和風のおつまみプレートなど、観光客にとって特別感のあるメニューが好評を得ています。
また、英語での乾杯の掛け声紹介や、箸の使い方を教えるサービスなど、小さな体験が強く印象に残ります。
単に料理を提供するだけでなく、五感で楽しめる体験を組み込むことで、店舗への満足度や
クチコミ評価の向上が見込めます。
メニュー設計やサービス企画の段階からインバウンドを意識することで、自然なかたちで訪日外国人客の心をつかむことが可能です。
インバウンド対策にかかる費用感と補助金活用
インバウンド対策を検討する際、多くの店舗が懸念するのが費用面です。
無理のない予算計画を立てるためには、施策ごとの費用相場を把握し、補助金制度を上手に活用することが重要です。
施策別の費用目安(MEO、SNS運用、多言語化)
インバウンド対策にかかる費用は、実施する施策の種類や外部委託の有無によって異なります。
たとえば、Googleビジネスプロフィールの最適化(MEO)を外部に委託する場合、月額3万円から5万円程度が相場です。
自社で運用を行えば無料で対応可能ですが、専門的な分析や競合調査を必要とするため、成果を重視する場合はプロに依頼すると良いでしょう。
また、SNS運用は、撮影・投稿・分析を含めて外注する場合、月額5万円から20万円程度が目安です。
そして、多言語メニューや店内案内の翻訳は、簡易的なものであれば数千円から対応可能ですが、写真付きのデザイン作成を含む場合は5万円から10万円前後が必要です。
店舗ごとの状況に応じて優先順位をつけ、段階的に投資していく姿勢が望ましいでしょう。
観光庁・自治体の補助金活用方法
費用面での不安を軽減するためには、観光庁や地方自治体が実施する補助金制度の活用が有効です。
たとえば、東京観光財団では「インバウンド対応強化事業」として、キャッシュレス導入や多言語対応の支援を行う制度が用意されています。
また、地方自治体によっては、店舗の外国語メニュー作成やMEO対策、SNS広告の費用を一部補助する事業が毎年公募されています。
申請には事業計画書や見積書、実施報告などの書類が必要となるため、事前に制度内容を確認し、スケジュールに余裕を持って準備することが大切です。
また、専門の行政書士や商工会議所に相談すれば、書類作成のサポートを受けることもできるため、不慣れな店舗でも安心して申請に取り組めます。
補助金を活用することで、限られた予算のなかでも質の高い施策を実現しやすくなります。
居酒屋・バーのインバウンド集客で失敗しないための注意点
インバウンド集客はチャンスが大きい一方で、配慮不足によるトラブルやクレームが発生しやすい分野でもあります。
スムーズな運営と高評価の獲得には、訪日客の文化や習慣を理解したうえで、事前の準備を行うことが大切です。
訪日客対応時のトラブル回避ポイント
インバウンド対応では、言語・文化・習慣の違いによって誤解が生じることがあります。そのため、トラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。
たとえば、予約トラブルの多くは「予約が成立しているかどうか」の確認不足に起因しています。
電話予約だけでなく、メールやチャットツールなどで確実にやり取りを残す仕組みを整えることで、誤解を防ぎやすくなります。
また、オーダーミスの原因としては、メニューの表記が曖昧であることや、料理の説明不足などが挙げられます。
外国語メニューには、辛さ・量・アレルゲンなどの情報を明示しておくことで、満足度と安心感の向上が期待できます。
さらに、支払い時の通貨やカード対応の可否も事前に分かりやすく伝えることで、混乱を防げます。
接客スタッフの基本的な英語対応や翻訳ツールの活用も、円滑な対応に大きく貢献します。
宗教食、喫煙・禁煙対応の留意点
宗教や生活習慣に配慮した対応は、訪日外国人からの信頼を得るうえで非常に重要です。
特にイスラム教徒のハラール対応や、ヒンドゥー教徒に対する牛肉除外などは、料理提供時に注意が求められます。
全メニューを対応させる必要はありませんが、豚肉・アルコール・特定の食材を含まない料理が明確にわかるようにしておくことが効果的です。
さらに、ベジタリアン向けの選択肢があると、欧米圏の旅行者にも安心して利用してもらいやすくなります。
また、喫煙に対する考え方も国ごとに異なります。分煙・禁煙の明示が不十分であると、健康志向の高い観光客からは敬遠される場合があります。
店内に掲示を行い、案内時にも丁寧に説明を行うことで、誤解を避けることが可能です。
小さな配慮の積み重ねが、良好なクチコミやリピーターの獲得につながっていきます。
まとめ
居酒屋やバーがインバウンド対策に取り組むことは、今後の成長と安定経営に直結します。多言語対応やSNS発信、文化配慮などを段階的に導入し、柔軟に改善を重ねることで、訪日外国人観光客から選ばれる店舗を目指せます。
インバウンドMEO 関連記事
- 自治体が行うべきインバウンド対策|訪日外国人を地域に呼び込む実践施策
- ウェルネス業界のインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- アパレルショップのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- ナイトライフ業界のインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- レンタカー業のインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- ネイルサロンのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- 美容クリニックのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- ドラッグストアのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- 歯科医院のインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法
- クリニックのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法